2001年1月中旬
コートを雪に濡らしながら、勉強に疲れきって大学から朝帰り…
そんな僕をレターボックスの中で待っていてくれたのは、
「Love Gallery」お年玉プレゼント、 性感ヘルス「池袋の王様」35分半額券。
がんばっていれば、いいことは自然と降ってくるものだな、と素直にうれしく思った。
それは一枚のペラペラなカードに過ぎなかったが、
今までネット上でなんとなく空想の世界のように見てきた風俗というものを、
一転して具体的な存在に塗りかえる一枚だった。
その第一の意味は、35分半額(4,500円割引)ということではなく、
割引券の有効期限が2月末に設定されていることだった。
2月末――2月末までのいつか、僕ははじめて風俗に行く。
延々と続く、軽すぎる一日にはもう我慢できないから。
エアコンの効いたこの部屋を抜け出して…
外へ出よう!
2001年2月16日
池袋北口から外に出ると、全天の青空と明るい日ざしのお出迎え。
見知らぬ街、それだけでも快い刺激なのに、
今日はもっと……ね。
Love Galleryで見た地図をたよりに、お店を探して歩き回る。
「へいわ通り」という商店街に入り、昔ながらの心地よい空気の中を少し歩いたところで、 お店の看板を発見。
目立ちすぎず隠れすぎない、バランス感覚の絶妙な看板だ。
そのあと携帯からお店に電話をかける。
周囲に聞こえると恥ずかしいので、電話ボックスに入ってこそこそと。
通話ボタンを押す瞬間、風俗に行くことが決定する。
…押してみた。ちょっと気が楽になった。
店員さん「はいこんにちは」
最初から店名を明らかにしないのは、この業界のルールなのだろうか。
少し聞き取りにくかったので、本当にお店につながったのかちょっと不安になったが、構わず、
よい子 「予約をお願いしたいんですが」
「ありがとうございます、どの娘にいたしましょうか」
「マナさんでお願いします」
「マナちゃんですね。コースの方は50分、70分、90分がございますが」
「50分でよろしく…お願いします」
「50分ですね。何時にいたしますか」
「え、今からでもいいんですか」
「えーとマナちゃんは12時出勤となっておりますので、12時以降になりますね」
お店のホームページで「早番」ということは調べてきたが、
10時開店と同時に出勤しているものだと思っていたので、少し意外だった。
「そうですか、じゃあ12時でお願いします」
「1時間前の11時に確認のお電話、11時半にご入店ということになります」
「確認の電話というのは、この電話にかけていただくことになるんですか?」
「いや、お客様の電話番号はご存じ…存じ上げませんので…」
「あ、すいません、こちらからかけるんですね。分かりました」
風俗のシステムというものを知らないので、こういう基本的な知識(おそらく)も初耳だ。
しかし別に恥じる必要もない、穏やかに堂々と電話を続けよう。
「お名前は?」
「****です」
「****様」
「それと、あの、インターネットのサイトで、35分半額券っていうのを頂いてきたんですが」
「ありがとうございます」
「これは、50分コースの割引券としても使えるんですか?」
「はい、差額でご利用いただけます」
「あ、そうですか。」
「では11時に確認のお電話、11時半にご入店ということでお願いします。ありがとうございました」
「はい分かりました、ありがとうございました」
最後は「失礼します」だろ、と自分にツッコミを入れながら電話を切る。
昔はピザの予約さえ緊張して辛かった僕も、ある程度は成長したといえるのだろうか。
思ったより店員さんも話しやすく、初めてにしてはスムーズに予約を入れることができたと思う。
さて、問題は時間だな。入店まであと1時間半か。
ここで時間をつぶしてもいいが、何か食べれば歯磨きしないといけないし、
ちょっと厚着すぎて汗もかいてしまったから、もう一度出直してくるとするか。
午前11時、再び池袋北口。
1時間前と同じ電話ボックスに入り、確認の電話をする。
最近は携帯の普及で電話ボックスもあまり見かけなくなったが、こういう時にはありがたいな。
「はいこんにちは」
「先ほど電話いたしました****という者ですが、確認の電話をさせていただきました」
「ありがとうございます。12時から50分コースで、マナちゃんですね」
「はい」
「お店の場所は分かりますか?」
「あ、はい」
「ありがとうございます。では11時半までに受付を済ませて下さい」
「はい分かりました、失礼します」
確認の電話は簡単だった。携帯をしまい、さっそくお店に向かう。
平日の昼間ということもあり、駅前から少し歩くと人影はまばらだ。
気の弱い僕でさえ、それほど人目を気にすることなくお店に入ることができた。
よくある雑居ビルの2階を目指し、駆け足ぎみで階段を上がってゆく。
思えば長岡のホテルでも、二人で階段を上がった。階段が人生のステップと重なる気がする瞬間だ。
見えないところから「いらっしゃいませ」という男性の声。カーテンを開けると、そこが受付だった。
気を落ち着かせようと少し試みてから、自分の名前を告げる。
中に座っているのは、電話に出た店員さんだった。
「基本のプレイはこのようになっております」
カウンターに貼られたプレイ表が指差される。
いわく‘Dキス・全身リップ・生尺・玉舐め・アナル舐め・69・素股・時間内無制限発射OK・指入れOK’。
「はい。」
「ではお値段はこちらの方で…」
受付を終えると、待合室に通された。
まだ心臓を高鳴らせているシャイな僕としては、先客がいなかったことが何よりの救いだった。
待合室は薄暗く、壁には女の子の写真が貼ってあった。
風俗系新聞の切り抜きなども貼られていたが、マナさんの登場回数は在籍する女の子の中でも一、二を争っていた。
意外といいところを狙ったかもしれない。
時計を見ると11時10分。あと50分か…
時間があきすぎていたので、店員さんには「一旦外に出ますか?」とも聞かれたのだが、
お店に出入りするときの恥ずかしさを考えると、しばらくここで我慢した方がよさそうだと瞬時に判断したのだった。
しかし、普段50分などすぐ過ぎてしまうのに、こういう状況ではどうしてこんなに時間を長く感じてしまうのか。
時間感覚の相対性を嫌というほど実感させられる。
待合室には、お店が紹介されているWebページを印刷したものと、JャンプやMガジンといった普通のマンガ、数冊の風俗誌が置いてあったが、どれを読んでも上の空で、気がつくと時計に目をやっている自分がいる。
心がこわばっているのが手にとるように分かる。
ときどき立ち上がって貼られている写真を眺めたり、流れている洋楽に適当にハモったりして気持ちを落ち着かせる。
11時35分頃、スーツ姿の客が入ってきた。
言うまでもなく僕は目を合わせず、風俗誌にひたすら視線を落としていた。
そのため彼について詳しいことは全く分からない。雰囲気からすると20代後半から30代前半といったところだろうか。
相手だって居心地がいいわけではなかろうが、なかなか落ち着いているように感じられる。
続いて2人目の客が入ってきた。こちらはもう少し年齢が上で、中年のサラリーマンのようだ。
金曜日の昼間ではあるが、二人とも何らかの理由で仕事の時間帯ではないのだろう、と好意的に解釈しておく。
11時40〜45分頃、二人の客に次々とお呼びがかかる。きっとメンバーなので5分前に来店ということなのだろう。
また僕だけが残され、プレッシャーこそなくなったが、それにしても時間の経過がいらいらするほど遅い。
これは決して、したくてしたくてたまらない、という類の気持ちではない
(その証拠に、まだ僕は全く勃起していなかったし、雑誌のヌード写真を見ても、全く反応する様子がなかった)。
そうではなく、この中途半端な束縛を誰かに解いてほしいという気持ちでいっぱいだったのだ。
一刻も早く、気の抜ける瞬間が訪れてほしい。
そう願いながら秒針の小刻みな動きを見守るしかなかった。
5分前。時間に牛歩戦術を仕掛けられたかのように、耐えられない状態が続く。
どんなにつまらない講義でも、これほど時の流れを遅く感じたことはない。
この辛さから抜け出すためにいっそ1Pでもしてやろうかと思ったほどだが、依然としてあそこは大人しいままだ。
息子になだめられ、僕はせいぜい歌を口ずさみつつ座っていることにした。
とうとう12時になった。お呼びはかからない。女の子の準備があるから、すぐというわけにはいかないのだろう。
あとは時間の問題と、気持ちは半分くらい楽になる。
10分過ぎ。ややおかしいな、と感じはじめる。さてはボッタクリか。僕はそんなにも運の悪い人間なのか?
そう思ったとき店員さんがドアをノックした。来たか!?
「すみません、マナちゃんが12時出勤ということになっているんですけど、
まだ来ていないみたいなので、すみません、もう少しお待ちいただけますか」
「あ、はい。」
そういうことなら仕方ない。僕は小さな本棚から雑誌を一冊取り出し、読み始めた。
12時を迎えるときとはがらりと異なり、気持ちの負荷が全くない状態で時間をつぶすことは容易だった。
あれから客もやってこない。興味のある記事の活字を目で追っているうちに、またノックが聞こえてきた。
「はーい」
「すみません、まだ出勤しないものですから。
こちらからも連絡はとっているんですが、もう少しお待ち下さい。
それとも、いま来ている女の子の中で気に入る娘がいましたら、そちらで遊んで下さってもよろしいですが」
「あ、じゃあもう少し待ちますので」
店員さんは、Nほほん茶を僕に渡して戻っていった。接客は丁寧で、好感が持てる。
温かいお茶を飲みつつ、僕は考えた。
今さら女の子を変更しても、その娘にとってはあまり面白い客にはならないだろう。
というのも第一指名ではないわけだから。
それと、これだけ待ったのだからマナさんに会えた暁には、ちょっとサービスが良くなるのではないかという下心もわいて出た。
どちらにしても、マナさん以外とはしないことを心に決めた。いっそのことマナさんが出勤するまでここに居座ってやろうか。
時間は1時20分。不思議なくらいあっという間だ。雑誌を読みふけっていると、
「すみません、まだ来ないものですから、ちょっと今日は…」
「ああ、そうですか」
「連絡なしでブッチするような娘じゃないんですけどねー。 何かあったんじゃないかって思うんですけど…
せっかく来ていただいたんで、他の娘と遊んで帰られてはいかがですか?
返金大前提ということで、こちらの写真をご覧いただいて…」
「いや、また明日来ますので」
「そうですか、では11時半以降にお電話下さい」
ここまで来ると意地もある。絶対マナさんにしてもらうんだ…
僕はお金を受け取ると、軽く一礼して『池袋の王様』をあとにした。
この日、帰りに寄った弁当屋で、お目当ての『メンチのりめんたい弁当』が、
昼間にもかかわらず売り切れていたのには愕然とした。
さすがにもう「出来上がるまで待つ」という気も起こらなかったので、 代わりの女の子ならぬ弁当を買って帰る。
これは、風俗などには行ってはいけないという、何かのお告げなのではないか?
まさか、行ったら性病がうつるとか?(マナさんごめんなさい、そんなこと絶対ないですよ)
いやいや、マナさんの方が僕の先祖の呪いで倒れてしまったとか?
オカルティックなことを考えつつ弁当を食べ終えたが、やはりお店に行く決心は揺らがなかった。
今日はもう寝て、明日に備えよう。
窓からのぞく明るい太陽にもはばからず、僕は外出着をぬいでベッドにもぐった。
まだ半分も経験していないとはいえ、はじめての体験だから、ちょっと疲れたかな。
2001年2月17日
なんとなく気持ちが昂ぶって、よく眠れないまま朝を迎えた。
昨日は、してはいけないと思いつつ2回もひとりエッチをしてしまった。
自制心の弱さには自分でもあきれてしまう。僕もまだまだ子供だ。
とりあえずタンパク質を補給すべきだと考え、Y野家で牛鮭定食をいただき、自室で牛乳を飲む。
親が送ってくれた高級な栄養カプセル(1個1,000円)を胃に流し込む。こんなことに使ったら悪いかな?
そうこうしているうちに、11時半が近づく。
もう一度Love Galleryを見て、もしマナさんが来ない場合には誰にしようか考える。
まずは今日早番で出勤する女の子しかダメだし、顔出しNGの女の子はちょっとリスキーだし、得意なプレイとかも気になるところだ。胸もある程度はあった方がうれしいし…
なんとか候補を絞って、電話をかける。さぁ、マナさんは来るかな?
結果。
来ない確率の方が高いなと思っていたのだが、「来ますよ」とさらり。
迷わず、1時に予約を入れる。
厳密にはメンバーではないが、すでに入店の実績があるので5分前に行けばいいらしい。
舞台は三たび、池袋北口。今度は本番です(誤解なさらぬよう。)
今日も晴天、冬空の下にも春めいた風を感じるすがすがしい一日だ。
ただ昨日と異なるのは、土曜日だけに、駅前を通り過ぎる人の数だ。
東口とは比べるべくもないが、Bックカメラもそこそこ繁盛している様子で何より。
人目が増えた分、初めてだったら少しためらったかもしれないが、
二度目なので比較的抵抗なくお店に入ることができた。
入口に、それらしい飾り付けがないのは風俗初心者にとって大変うれしい。中に入ってしまえば、こっちのものだ。
受付で支払った料金は11,500円(入会金2,000円+昼の50分コース13,000円+指名料1,000円−35分半額券4,500円)。
待合室には先客2名がいたが、どうやら同僚を連れてきただけのようだ。
大声で話が弾んでおり、入るときこそ気がひけたが、なかなか興味深く聞き耳を立てさせていただいた。
話の中で「風俗っていってもね、イケないときも結構あるよ。なんか<タイマーが>ピピピって鳴って、終わりです、って言われて」というのが特に印象に残った。そういう話は他でも聞いたことがあるが…実際そうらしい。
まぁ、僕は感じやすくて早漏だから大丈夫だろうけど。
その2人が同僚のプレイ終了とともに帰っていって、僕ひとりだけが残された。
時計を見ると、1時まであと5分。
昨日は本当に、秒針の回転が歯がゆいほど遅く、1分1分がものすごく長く感じられたけど、今日はそうでもない。
比較的落ち着いて、その時を待つだけ。
落ち着きすぎて、テンションが低いのがむしろ気になる。こんなので大丈夫かな?
さて何を話そう。ネタは昨日からいろいろ考えてあるが…
まぁ自然に流れの中で話題をつくっていけばいいんだろうけど…
よく考えればホストでもないのに、無用な心配をしてしまうところが僕らしい。
そう思って少し苦笑する、ハハハ、そう、笑ってれば大丈夫。
1時をまわる。待合室に置かれたテレビは小さな音量で、何やらバラエティ番組を映し出している。
僕はそれに構わず目を閉じる。店内に流れるR&Bのビートが、静かに身体の芯を打つ。
メロディをささやかに口ずさむと、いつもの僕が戻ってくるような気がする。
いや、‘いつもの’じゃなくて、‘いい方の’自分が。
トントン
「お待たせしましたー」
店員さんがドアを開け、僕は通路へ通される。
店に入ったときから目にしていたアイボリーのカーテン、それを開けるのは自分の左手。
「はじめまして。指名ありがとう」
「こんにちはぁ」反射的に頭が下がり、声が出る。
意識しなくても、普段とは違う猫なで声を出してしまうところがやはり僕らしい。
自然な感じでそこに立っているのがマナさんだった。
シャワーに入るからか、髪をしばっているので見た目の印象はネットとやや違う。
身に付けているのはランジェリーだが、不思議なほど自然な感じがする。
どうしてだろう、女の子の下着姿なんて現実には(あのとき以外)見たことないのに。
どうしてこんなにストレートに受け入れられるのだろう。
期待は高まるものの、熱い興奮がわきおこるというわけではなく、普通に接することができる感じ。
思春期の激しさは僕の中から去り、別の何かが育ってきたことを感じた瞬間でもあった。
二人で個室に入る。必ず客を先に部屋に通す、という点は業界の常識なのだろう。小さなことではあるが感心に足る。
「昨日はごめんねー」
「昨日はどうしたんですか」
「昨日はねー、体調が悪くて」
「大変なんでしょうね。 昨日は、1時間くらい待ってて、いろんな人が見れて面白かったです。
なんか接待かなんかで、自分はしてもらわないで、待ってるだけって人も結構いるんですね」
とりあえず話をしなきゃいけないという思いから、ややウソをついていることが読者の皆様にもお分かりだろう。
あまり待っていたと言うと悪いかなという気もして(それなら言わなければいいのだが)、
よく分からない会話になっている感もある。まぁ初めてなので自分でも大目に見たい。
それと一部の読者の方は、上記の会話に著しい違和感を感じるかもしれない。
丁寧語を使っているのが客である僕であり、タメ口なのがマナさんであることに対してである。
しかし僕は基本的に初対面の人に対しては丁寧語が口をついて出てくるので、別に距離をとっているわけではなく、これがあくまで自然体であることを理解してほしい(ちなみに、初めて後輩と話をするときはかなり意識した)。
マナさんもプロだから、僕の口調に合わせて、あえて自然な雰囲気を崩さないような話し方をしてくれたと考えることができる。後でも出てくるが僕はマゾっ気があるので、これが一番身体に合うのだ。さらに同様の理由で、マナちゃんとは呼びません。
「服はここに脱いでね」
基本的な流れとして、まずシャワーに行くということは頭に入っていたが、それと服を脱ぐという行為がなぜか結びつかず、不思議な雰囲気のなか一枚一枚脱いでいく。
一応、お気に入りのシャツとトランクス、ソックスを身につけて来ているあたりは、自分で言うのも何だが、けなげである。
そのあいだにも、もちろん会話は進んでいた。確か、インターネットでこのお店の半額券が当たらなければ、来店する勇気はなかっただろうということ、去年10月ごろに初めて風俗に行こうと決心して、8,000円もする中国エステに入ったが、韓国エステなどと違ってHなサービスがなくてがっかりした、つまり風俗は初めてということを話した気がする。
先ほどの心配はどこへやら、なかなか好調なしゃべり出しだ。
見ると、知らない間にマナさんはランジェリーを脱ぎ、胸も露わな格好でこちらを見ていた。
脱ぐ過程に色気を感じる僕としては、少し物足りなさを感じてしまったが、50cmほどの距離を隔てて、会話と脱衣が全く自然に行われてゆくこの状況には、さすが風俗店という印象を受ける。
また、その状況にいとも簡単に順応している自分がなにより意外だった。
思ったより自分が大人になっているというか、良い意味で自己認識と現実がややずれてきていることを、この文章をまとめる中で感じている。
先ほども書いたが、少なくとも思春期が終わったことだけは間違いなさそうだ。
まだ激しさがあり、極度に内気だったころにこういう状況に置かれていたら、僕はどんな行動をとったのだろうか。今となっては知るすべもない。
すべて脱ぎ終わると、タオルが渡されたのでそれで隠すべきところを隠す。
そのまま、ベッドに座って話を続ける。寝るために作られたわけではないそのベッドは、鮮やかなピンク色をしていて、普通では考えられないほど高さのないものだった。
ベッドの中ごろと端っこ、互いの腰掛ける位置もなかなか微妙だ。
もっとくっついて良いものだろうか、別に遠慮しているわけではないが、会話が十分に理性を保っているだけにいちゃいちゃするという雰囲気ではない。
「僕、ちょっとエッチなサイトとか作ってるんですけど、10万人くらいのお客さんが来てくれて」
「あ、すごい。どんなサイト?」
「ひとりエッチとかの…」
「面白いねー。iモードで見れる?」
「iモード… たぶん見れると思いますよ。前、携帯で見てた人いるし…」
話を止めることなく、2つ隣のシャワー室へ向かう。ここまでで約10分。
「シャワー入りまーす」
おそらく、シャワー室の中に先客がいないかチェックするための言葉らしい。
シャワー室は小さいながらも、明るくて清潔な感じを受けた。
風俗について知識のない僕は、タオルをどうしたらいいのか、シャワーは一人で入るのかどうかも分からず、ちょっと迷ったふうにしていると、
「大丈夫、マナも一緒に入るから」
小さなシャワー室に二人入れば、身体の間隔は20cmくらいになってしまう。
当然お互い裸、こんな状況は生まれてから初めてで、すぐにでも性欲を解き放ちたい衝動に駆り立てられてしかるべきなのだが、会話があまりにもナチュラルなので、この状況さえも‘あり得る’ものに思えてくる。
あのときの様子をいま思い返してみるとある程度の興奮を禁じ得ないが、実際に二人でいた時間には、至極冷静に話をつないでいた自分が可笑しいほどだ。
僕が‘ひとりエッチの’サイトで、中学生から人妻に至るまでさまざまな女性と知り合って、でも実際にはなかなか会えないということ。去年は、その中のひとりと身体の関係も半分くらい経験したけれど、そのあと信じられない地獄を見たこと。慰謝料5万円に比べれば風俗の値段なんて安いものだと思っていることを話すと、マナさんは「ふーん」と言いながら聞いてくれた。
一方彼女は、携帯で毎晩‘エロサイト’を見てまわるのが好きだという。
携帯って画面小さいから見にくくないですかとたずねたら、最近は画面も大きいし…とのこと。
パソコンは買わないんですかと聞くと、「お店の人にも『マナちゃん、絶対買いなよ』って言われるけど、私、メカ弱いから」買わないんだって。
形の良い胸を目の前に、さすがに僕も何かが立ち上がってくるのが分かる。
そこをまた自然な手つきで、シャワーのお湯とマナさんの指が洗ってゆく。
どうなんだろう、ここで我慢できなくなって抱きしめちゃう人もいるんじゃないかなぁ。
今日の僕は、マナさんに対して欲情するというよりは、話しやすい友達がいっしょにいるという感じで楽しんでいたため、身体を触りたくなるとかそういう気持ちにはならなかった。
マナさんは、本当に聞き上手で話し上手でもあり、何よりさっぱりとした性格が心地よい。
こういう仕事をやっていて一番身につくものは話術なのだろうな、と改めて感じさせられる。
そして、僕は何を求めてこの店にやって来たのかということを考えるに、きっかけはもちろん性欲に違いないが、本当に求めるものは他のところにあるのではないかと思わざるを得なくなった。
自分が求める‘癒し’は、身体に対するものではないのかもしれない。
まさか、ただ話し相手が欲しくなっただけ? それはちょっと淋しい結論だが…
少なくとも異性の話し相手なんていないから、実のところそんなものなのかもしれない。
話をするためだけに支払う11,500円、高すぎると決め付けることは誰にも出来はしないはずだ。
褐色の液体が注がれたコップに、シャワーのお湯が満たされて消毒薬の出来上がり。
僕はそれを渡されて、うがいをした。
風邪の予防用に売られているイソジンだが、実はほとんどの風俗店で、口腔消毒薬として使われている。
マナさんも別のコップで何回かうがいをして、シャワータイムは終わった。
「ピンサロなんかはシャワーもなしで、いきなりフェラとかするから、衛生面ではずっと性感<性感ヘルスのこと>の方が上だよ」と言ったマナさんだが、風俗を商売として成立させる上での最低限のルールを、ここに見たような気がする。
シャワーを出て、再び個室に戻る。並んで座って、飽きずにおしゃべり。
何かの話題から、自分が大学2年生であることを告げると、
「大学2年…ってことは何才?」
「二十歳です」
「そっか…見た目と違うって言われない?」
「そう、言われる…そこのお店<中国エステ>でも、なんか身分証明書見せて下さいって言われて、
免許を出したんだけど‘昭和’っていうのが分からないらしくて。中国人だから。 それでなんか半信半疑で通されて…」
「ああ、それは年下に見られたっていうことね」
「えっ、年上に見えますか? えー、それは初めて言われた。何才くらいに見えます?」
これには本当に驚いた。まさに史上初だ。老けてるっていう意味じゃなければいいけど。
「22か、23」
「へぇー」
「あのね、見た目じゃなくて、話し方とかしっかりしてるから、それくらいかなって。
今さぁ、高校生くらいでも外見じゃ分からないじゃない、でも話し方で、マナ、分かるのね。
たまに高校生とかお店に来るんだけど、見た目大人っぽくても話し方が『なんとか、でぇー』とかだと、
(あー、こいつは高校生だな)って分かるの。それで歳聞くと、『17です』とか。」
かなわないな、と思った。
きっと簡単なウソをついても、バレてしまうんだろうな。
人を見る目が育っていない僕としては、そんな能力もできれば身に付けたいものだ。
「わたしは18なんだけど、2年くらいこの仕事やってて、いろんなお客さんに当たってきたから、
自分では何も知識とかないんだけど、どんな話題がふられても相手ができるようになったのね」
「ああ、僕もそう。自分は大したことないんだけど、 周りの友達が頭いいから、知識は身についてる」
「そういうのって絶対あるよね。
こういう仕事だと、同い年くらいのお客さんって少ないから、<歳の離れた客に話を合わせると> 話がババくさいとか、落ち着きすぎてるって言われて、本当より歳、上目に見られるんだ。
世間のイメージだと、もっと18才って違うじゃん。
なんかもっと、街を歩いてるような18才の女の子って違うでしょ」
「うんうん」
「でも本当はまだ18なんだぞ、ピチピチなんだぞって言いたい」
そう言って彼女は笑った。
「でも、大学院で何かを研究してますー、とかいう人が来ると、話が全部‘真実’で、
マナが『それは何とかなんじゃないですか』って言っても 『いや、それは何とかだ』って切り返されちゃって、
全然、今みたいに、話のキャッチボールができないのね。
それで(なんか、つまんねーなぁ)って思うんだけど、
聞いてると、やっぱりちゃんと勉強してるだけのことはあるなぁ、って思うよ」
それは本当によく理解できる。
特に理系の人間は、自分の知識を当たり前のもの、誰でも理解しうるものだと勘違いしてしまいがちで、独り善がりな話を延々と続けるきらいがある。
僕は理系の専門家として、もちろん今後豊富な知識を身に付けていかなければならないが、そのベースに常に人間らしさを失わず、いつまでも普通の感覚でおしゃべりができる人間であり続けたいと思っている。
そういう意味で、マナさんの言いたいこととはやや違う方向ではあるが、大変共感した。
そして何よりうれしかったのは、「今みたいに、話のキャッチボールが」という部分で、
大げさな表現を使えば‘僕の会話能力が評価された’ことに他ならない。
話し下手で、他人とのコミュニケーション能力が劣ることをひとつのコンプレックスとして抱いている僕としては、
状況的に何%かのお世辞が入っていることを差し引いても、この言葉は何よりのプレゼントだった。
「じゃあサービス始めまーす」
ここに通されてから、25分くらい経過したころだろうか。
話がひと段落ついたところで、やや唐突にそれは始まった。
もう二人とも服は脱いでいたから、僕のしたことは、タオルをとってベッドに横たわるだけだった。
僕の太ももを挟み込むようなかたちで、彼女は立てひざの姿勢で上になる。
さらさらしていて、引き締まった脚の感触が伝わってきて、
僕のスイッチを‘会話モード’から‘Hモード’に切り替えようと働きかける。
そのまま彼女は倒れこむようにして、僕の乳首を狙ってくる。
さっきまでの、親しみやすい友達の表情が、いつの間にか‘女’に変わっているのはさすがだ。
最初は舌で、次は唇で、僕の一番感じる突起を責め立ててくる。
乳首舐めを体験するのはこれで二度目だが、女の子のざらついた舌が軽く先端をかすめるだけで、僕の身体はビクンと硬直して声が漏れてしまう。
「あっ、ダメ……責められると、声、変わっちゃう…ふあん」
その震えがまだ止まらないうちに、柔らかなリップが性感帯をくるみこむような胸へのkiss。
先端が吸い摘まれ、小さな突起がざらりと強く舐め上げられたかと思うと、
ひらひらと舌が小刻みに何度も往復して断続的な快楽が意識に突き刺さってくる。
彼女の舌から流れ出すローションが、最初は温かくてそれで冷たくなって…その液体感に加え、ピチャピチャという唇の音がたまらなくいやらしくて、目を閉じると本能にまで届いてくる。
「あぁxtyx、乳首すごく感じるんですよぉ、うあぁ」
「フフ、どっちかっていうとマゾな方じゃない?」
「そうですー、分かりますぅ? ずっと前からマゾだから…」
彼女は僕を、女の瞳で見つめて、
「そう、あたし、責めるの好きで、ちょっとサドだから」
互いを指差して、
「相性いいかもよ」
そのまま抱き合うようなかたちに崩れてゆく。
彼女の全身が僕に覆い被さり、胸の感触が、脚の感触が、あのあたりが、ひとつになって女性の身体を感じはじめる。
そしてキスの予感がしたから、
「キス、まだしたことないからぁ、ちゃんと教えて。」
「えっ、本当に?」
彼女は本気で驚いているようだった。僕がうなずくと、何も言わないで、ゆっくりと唇を重ねてきた。
時間をおかず、二人の舌が触れ合う。
彼女の舌はなんともいえない動きをしてきて、絡み合い、摩擦され、僕はそれについていくのが精一杯だった。
僕は両腕を彼女の背中に回して、いままでより少し強く抱きしめた。
意識はまだなぜか冷静さを保っていて、自分のファーストキスを冷静に分析していた。
それは無味で、ほのかに消毒薬の香りがした。
思ったより舌って硬いんだな、と思った。
意識次第で柔らかくも、硬くもなる不思議な軟体。
その感触を、僕は女性の身体全体の感触とともに楽しみ、学んだ。
唇を離すと、彼女は言った。
「大丈夫。」 …あるいは「大丈夫?」だったかもしれない…
「…分かんない」僕は小さく笑った。
彼女の唇はそのまま僕の首筋にまわり、ゆっくりと、時に速く妖しく、皮膚の表面を舐め上げてくる。
男の弱点を熟知した彼女の責めに、
このあたりもかなり感じてしまう僕は、高いトーンの「あぁぁ」をそのたびに封じることができず苦しんだ。
彼女の温度が耳にさしかかる頃には、性感もいよいよ露になり、
舌がどこか皮膚や髪の毛に触るたびに、背筋の痙攣を抑えきれず、快楽をそのまま表現してしまうほどになっていた。
次は快楽が下の方に降りていった。全身リップとよばれる性感ヘルスらしいサービスによって、僕の腹部は未知の刺激にさらされた。
それに加えて、わき腹のあたりを彼女の指、もしくは爪が素早く伝うたびに、信じられないほどの鋭さで快感が走るのだ。
それが二、三回繰り返された後、今度は舌が同じところにラインを引く。
「はぁぁあ」ため息が出るほど心地よい夢を見る。
とうとう彼女の舌は、降りるところまで降りてきてしまった。
熱いところが五本の指で支えられ、温度をもったやわらかいものが覆い被さってくるのをぼんやりと感じ取る。
それは柔らかい摩擦とともに根元へとさらに降りてゆき、感じるところが全てつつみ込まれる。
身体の一部だけがなま暖かい感触にさらされ、
先刻自らの舌と唇で感じ取ったあの生き物が、敏感なところを責め立てているのが伝わってくる。
彼女の唇が段差をこえるたびに欲望が送り込まれてくる。
彼女が口を上下させるたびに、さわさわと下腹部を撫でる髪の感触が正気を徐々に失わせてゆく。
くちゅくちゅ、ぴちゃぴちゃという音が絶えず耳に届き、いまの自分の状況を客観的に教えてくれる。
フェラチオされてるっていうことを理解し、初めての快感に理由づけをしてゆく。
その間にも僕は女の子のようにあえぎ、出る声を留めることができない。
やがて彼女はそこから口を離して、その下についている部分を舐め上げ始めた。
ふにゃふにゃした部位に彼女の舌が弧を描き、線を引く。
球状のキャンバスに絵を描く…そんな表現はおかしいけれど、性感を鼓舞するリズム感はひとつのアートでさえある。
なかば放心状態の僕をおいて、彼女はベッドを一時はなれ、すぐにローションを持って戻ってきた。
僕の太ももをまたぎ、直立した部分とその周辺に満遍なく、とろとろとした透明な液体が塗られてゆく。
「ねぇ」
「え?」
「ん…たぶんすぐイッちゃうから、ぁ…」
彼女は自らの内腿にも粘液をたっぷり塗りたくり、よく見えなかったが、たぶん右手も十分にとろとろにして、僕の方へ倒れこんできた。
弾力のある胸を僕の身体に押し付けながら、
右手はあふれる液体のなか、しっかりと芯をとらえ、慣れた手つきでゆっくりと動きをはじめる。
僕は1Pのときもローションをたまに使うから、このぬるぬる感にはある程度耐性ができているが、彼女の温度が加わって、体重を半分かけるようなかたちで上下前後になまめかしく動かれると、どうしても感じはじめてしまう。
「あぁ」と声を出しかけたところに、彼女の唇が僕を塞ぐ。
先ほど教えてもらったばかりの舌の動きがまた、僕の口の中で繰り返される。
舌がつつかれ、舐め回されると同時にあそこがしごきもてあそばれる。
彼女は口と口のすき間から、ときどきあえぐような声をあげて僕を楽しませてくれた。
ただ、ローションで滑りがよいだけに、それほどあそこは強い摩擦を受けていなかったので、
(まだ、がんばれるな)ってちょっと甘い考えを抱いた。
すると、その考えを見透かしたように、
「まだ、大丈夫だよね?」
僕は見つめてうなずいた。すると彼女の舌は耳に向かう。あぁそこは感じすぎるからダメなのに…
「あああっ」
あそこは同じ速度で責め続けられている、さらに耳にかかる彼女の吐息と、性感の尖端を的確に攻めてくるリップ攻撃に僕は次第に追い詰められていった。
僕はもっと密着感が欲しくて、左腕を彼女の背中にまわし、次いで右手を添えた。
彼女はそんな僕の動きには構わず、ポイントを耳、首筋、唇へと小気味よく移動しながら、にゅるにゅると局部を擦ってくる。
「あぁぅ、乳首も…責めて」
「なに?」
激しい責めを続けてきたとは思えないほど、しっかりとした声で彼女は聞き返してきた。
これくらい何でもないのだろう。童貞の性欲を処理するくらいは。
「乳首も、責めて」
彼女はそれにすばやく応えて、攻撃の重点を乳首に移してきた。
こうなると僕は全く抵抗する術を知らない。
欲望がとたんに制御できなくなり、自分の上で前後左右に動く彼女、プロの舌技でもって無力な乳首をあやし、いじめる彼女をなんとなく見つめながら、今までとは違う高まりが下半身にうごめき出すのを感じていた。
刺激的なリズムでひとときも休むことなく、快楽の出口をねちゃねちゃと責め続けられている以上、高まりを抑えたり鎮めたりすることができるはずもない。
蛇口がひねられ、コップに水がたまっていくようなイメージで、
性欲はコップの中ほどを超え、7分目を超え、…
その量とともに、僕の情けない声はトーンを上げてゆき、その質もさっきまでとは全く変わってきたことを自覚する。
彼女もそれに気づいたのか、今まで遊ぶように動き回っていた舌をディープキスに専念させ、クライマックスの舞台準備を完了させる。
全てが導かれていく中、僕の欲望は果てを迎える。
彼女を抱きしめながら、ねちねちという音の内側で、
まるで表面張力の支配下におかれるような10秒間に突入する。息は荒れ、意識がさまよってくる。
「あああああ、ダメぇ…」
性欲はとうとう僕の縁からはみ出し、もはやどんな手段をもってしても吐出を抑えることはできないという諦めが広がる。
自分で自分をしごくときなら、その瞬間に手の動きを止めてしまいそうになるが、彼女は最後の最後まであそこ全体への刺激をやめようとはしない。
彼女の指先から淡々と気持ちよさが染み込んできて、
とうとう表面張力を破り、
コップから液体がこぼれ
「あああああぁ」
…噴いた。いつもだったら空気中に放たれる精液が、今日は彼女の身体にすべて撒き散らされた。
ローションのねばねばの中で、僕の白さはどの程度散ったのだろうか。
急激に醒めてゆく性欲にもかかわらず、
ほのかな余韻が去りきるまで、彼女の手はゆっくりと僕のかたまりを撫でていてくれた。
その間10分。文章で書くと長く感じるが、実際のところあっという間だった。
一人でするときだったら、早いときは30秒だけど(笑)遅いときは30分くらいかけるからなぁ。
マナさんは何枚もティッシュを引き抜いて、後始末をしてくれている。
なんだか最初から最後まで、彼女とかじゃなくて友達にしてもらっている気がして、なんとなく恥ずかしかった。
「サービス始めまーす」と言われるまで、普通の話をしていただけに、
そのあとの急激な変化に頭がちょっとついていけなかったのかもしれない。
最後もちょっと意識して…マナさんが一生懸命動いているから、そして時間制限があることを考えて…イクのを早めてしまったし。 もう少し我慢した方が良かったかな。
そんなことを考えながら、ぼんやりと薄暗い天井を見ていると、
「敏感なんだね」
ねばねばを拭き取ったあとのマナさんが、友達の表情に戻って笑いかけてくれた。
「え…なんか恥ずかしいです」
僕も照れ隠しに笑ってみた。
「でも、その恥ずかしいのが、逆に快感とか。」
「そうかも。」
そうなのかな? どうでしょう。
「普通男の人って声とか出さないでしょ」
「そう…みたいですね」
くすくす。
「でもね、私サドだから、大きい男の人とかでもプレイに入ると『ああ』とか声を出してくれると、
すごくいやらしくてうれしいのね」
じゃあ、少しはよろこんでもらえたのかな?
「でも…彼女いないの?」
「いないですよぉ。」
「そうなんだ…お店やってるとね、もう本当にすっごい太った人とか来るのね。
それで、『いま彼女いないんでー』って言うんだけど、 『ちょっと海外行っててー』とか言って、
『お前彼女いるんか!』みたいな」
「あはは。え…でも男子校だから…」
「ああ、私も女子校だったからそれは分かるー」
「中高…中学校と高校、6年間男子校だし、 大学でもいま工学部だから、男子校みたいなもんだし」
「そうなの…でもクラスに女の子いるでしょ?」
「いますけど、3人くらいだし、かわいい子は1人とかだから」
「ふーん」
その1人と仲良くなれるわけないじゃないですか。マナさんっ。
「でも、いろんなお客さん見るけど、…そういうふうには見えないけどなぁ」
またまたぁ、そんなお世辞言ってもダメだって。
「そうですかぁ?」
↑お前も乗せられるなっつーの。
「絶対、いじめてくれる子ができると思うけどなぁ。」
そう…誰かいじめてくれないかな…優しくいじめて欲しいなぁ。
毎日毎晩、いっしょにそばにいてくれて、やさしくしてくれる人、いたらいいなぁ。
マナさんの言葉はお世辞だと思うけど、百歩譲ってお世辞でないとしても、
そんなに世の中甘くないみたいで、ちょっぴり辛いです。
‘サービス’が終わってから5分、ピピピピッとタイマーが鳴った。
これで最初から40分。二人タオルを巻き、シャワー室へ。
「これ、35分コースだったら大変でしょうね」
「うん、だいたい普通は50分なんだけど、
どのコースでも最後はシャワーゆっくり 浴びたり、服着たりで時間かかるから最後の10分はまずとってあるの。
35分だと話とかほとんどしないで、ダッシュでシャワー入って、 それでも5分くらいかかるから、残り20分でしょ。
もうやってる間もほとんど無言! だからサービスもなんか義務的になっちゃうよね」
お互い、ローションと他の液体でべたべたになってしまったところを、シャワーの温水が洗い流してゆく。
こんな狭い空間に二人だけで、裸同士でいることさえ何の不思議でもなく、
ふつうに風呂の中で友達としゃべっているような(注:僕は寮に住んでいるので)心地よい感じだ。
消毒液を含んだあと、僕は思ったままを口にした。
「でも、思ったより入りやすいところだし、また来れるかもしれない」
「うん、そうね、全然入りやすいでしょ」
「大通りから一本奥に入ったら、あんまり歩いてる人いないですよね。
人目とかそんなに気にならなかった。今日は土曜だから、昨日よりはちょっと多かったけど」
「そう。それに、この通りは風俗のお店多いから、このあたり歩いてる人は半分くらい風俗の関係者だよ」
「へぇ」
「あとは、お店入っちゃえば、みんな仲間だからね。
みんな抜きたくて来てるからお互い様だし」
この人いいなぁ、なんかさばさばしてて、話してて飽きない。
風俗とはいっても、50分のうち40分はトークなのだから(エッチを長くしても30分くらい?)、
話がつまらなかったらどんなに味気ないことだろう。
少なくとも今回に関しては、抜いてもらったことより話の方により大きな価値があったような気がする。
ピンク色のタオルで身体を拭いたあと、部屋に戻って服を着る。
もうタイマーはかかっていないので、50分という時間制限に対してそれほど焦る必要はない(常識の範囲内で)。
僕が服を着る間、マナさんは部屋の隅っこで何か書いている。
客のメモでもとっているのだろうか? それでも話し掛けるとちゃんと応えてくれる。
「彼女とかできると、結構お金かかるからなぁ」
「そう、女ってめちゃくちゃお金かかるからね。 面倒だよー」
「2日前もバレンタインだったけど、 もらった人はもうお返しのこと考えたりとか」
「そうそう」
「だから、1か月とか2か月に1回、こういうところに来ても、
結局はそんなに変わらないんじゃないかなって思う」
1か月はさすがに極端な話だが、2か月2万円だったらだいたい妥当な線ではないだろうか。
「そうねー、お客さんでもそういう人いるけど、
中途半端に楽しい時間を過ごして、それで家に帰ってからの 淋しい時間が耐えられないっていう人が多いね。
だからオプションで何か持って帰れないのーとか聞いてきたりする」
「ふーん…僕はひとりには慣れてるから、淋しいとかそういうのはないんだけど」
風俗は、愛情や長時間のふれ合いを得られない点が致命的な弱点だが、
相手に気を使う義務がなく、浮気OK、後を引かないことなど気軽なところはもっと評価されてもいい。
特に僕は長岡事件で、恋愛沙汰の最も嫌な部分だけ、まさに煮え湯を飲まされたので、
このようなイージーな関係で性欲さえ満足させられるなら、サービス業のひとつとして積極的に利用してもよいのではないかと考える(もちろん働いている身分ではないから、今までの消費バランスを崩さないように自制しなければならないのは当然であるが)。
ファーストフードは栄養がないけれど、たまには食べてもいいでしょ、という感じと似ている。
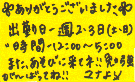
「あと、これ…」
黄色いカードを手渡された。名刺である。先ほど彼女が書いていたのはこれだったのか。
「忘れ物ない?」
「うん…あ、ちょっと待って」
腕時計をつけ、コートを羽織る。ひとりでも当然着られるけれど、マナさんが手伝ってくれるからそれに甘えてみた。
ファンヒータで暖められている部屋から、外へ出る。
>エアコンの効いたこの部屋を抜け出して…
>外へ出よう!
外へ…
「ありがとうございましたっ」
僕も同じ言葉を返し、カーテンを開ける。店員さんにも軽く頭を下げ、階段を下りてゆく。
外へ…
商店街に飛び出す。買い物袋をかごに入れて通り過ぎるおばさんの自転車、荷降ろしの軽トラ、青い空。
午後2時の池袋は明るくて澄み切っている。
シャワーで少しだけ濡れた髪を気にしながら、僕は街の中を歩いてゆく。
人ごみの中、駅の中、通り抜けて。
東口で信号を待つ人たち、僕だって自然にまぎれ込める。
こんなに苦手だった街の空気、ひとりという心細さ、
嘘のように心は軽く、このまま帰ったら何かもったいない気さえしてきた。
自分のスタイルが、だんだん自己肯定できるようになってきた。やっと。
信号は青、
強気の心で外へ出よう。
生まれて初めて、服でも見てくるかな。
忘れかけていたひとときの自由と冬の空気を、僕は思い切り吸い込んだ。
青くて広い空の下、ほのかに残るイソジンの香りは、
そう、ファーストキスと、
自由の香り。