 |
||
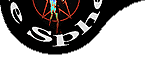 |
The Albums Of Rush index | Home | BBS | What's New? | Links |
|
 |
||
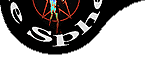 |
The Albums Of Rush index | Home | BBS | What's New? | Links |
|
The Albums Of Rush"Counterparts"
General talking for this albumGeddy Lee: We've been moving in this direction over the last two or three records. slowly eliminating frills and traying to get a more rooted, more hard-hit-thing, basic sound. Anti-technology. (Network Nov., 1993) Producer: Peter Colins-----プロデューサーを、引き続きピーター・コリンズにしたのは、前作のサウンドと方向性を気に入っていたからですか? Alex Lifeson:前作、前々作ではルパート・ハインがプロデューサーだったけど、もういいだろうということになってね。楽しかったけど、そろそろ前進する時期かなと思ったんだ。で、またピーターと一緒にやるのもいいかなと思ったんだ。彼とは以前『ホールド・ユア・ファイアー』や『パワー・ウィンドウズ』をやったけど、当時彼が果たした役割は今とはかなり違う。そのあとピーターはアリス・クーパー、インディゴ・ガールズなどとやって、多彩な経験を積んでいて、まったく新しいビジョンを持つようになっていたんだ。すごく強烈なギター・アイデンティティを持ったアルバムを手がけたことがあったしね。例えばクイーンズライチの『エンパイア』は彼が誇りにしていい作品だと思う。何より彼は素晴らしい人物だし、責任感に溢れているからスタジオでは何の心配もいらない。彼が完璧に仕切ってくれるから、僕たちは音楽だけに専念できる。新しい人とやって新しい経験をして、その人のやり方を学ぶのもいいけど、ピーターとはまたやりたいね。彼とスタジオで過ごしたのはすごく楽しい経験だったよ。それが大切なんだ。前進すると共に楽しみ、仕事っぽくなり過ぎずに音楽から感情を引き出すことができるというのは大切だよ。(Guitar Magazine 1994年2月号) Neil Peart:プロデューサーのクレジットという点では、ルパート・ハインとピーター・コリンズは私達よりも前に名前を置くようにしている。二人にはかなり敬意を払っているんだ。(Burrn! 1994年1月号) Recording Engineer: Kevin (Caveman) ShirleyGeddy Lee:実はこのアルバムは、“音”に関するはっきりとしたゴールを持った、数少ないアルバムの一つなんだ。いつもはレコードが自然に作る形に任せるんだが、今回はまずサウンドを変えたかった。『ロール・ザ・ボーンズ』にも『プレスト』にも気に入っている部分はたくさんあるけど、もっとアグレッシヴな音にした方が良かった部分もあったんだ。どちらもミックスの段階でそれに気が付いたんだよ。もう少し大きな音にしたいとか、もう少し密度の高い音にしたいとか思っていたんだが、テープに入っている音では無理だったんだ。 Alex Lifeson:ケヴィンは“ストレートにプラグを突っ込んで、すべての目盛りを最大に上げて録音する”派の人間なんだ。ドラムに対するアプローチも同じさ。ボードの EQ は一切使わないでドラム・マイクをセットし、それを彼の頭の中にあるベストの音が録れる場所になるまであちこち動かすだけなんだ。最近一緒に仕事をしたエンジニアたちと比べたら彼のアプローチはむしろ原始的で、決して洗練されたエンジニアリングではなかったけれど、僕たちが期待したとおりの結果をもたらしてくれたよ。(Player 1994年4月号) Album ThemeNeil Peart:基本的には曲を書いた後で、最後にタイトルを付けたんだ。全曲終えてから誰もが気に入るようなタイトルを私は必死で探していた。(笑)そうして、大部分の曲が二重性、つまり一つのものとまた別のものとの対比のようなことを扱っていることに気付いたんだ。この“Counterparts”という言葉は、“Animate”の中の“My counterpart-my foolish heart”という一節に出てくるもので、この言葉をタイトルにするのはどうかと考えるようになった。実際に辞書で調べたら、“相対するもの”と、同じなのに違う“一双のもの”という両方の意味があったんだ。私には、これが“敵”という意味での“相対的なもの”に留まらず、“同じだけど違うもの”という、すごく特殊な言葉だと思えたんだよ。反対のものと揃いのもの、そのどちらも意味するという事を考えると、脳味噌が疼くよ。(笑)(Burrn! 1994年1月号) Animateライヴ演奏:Counterparts tour, Test For Echo tour Neil Peart:“Animate”は、男性であっても女性であっても、すべての人の内側には異性の部分、“counterpart”があるという考えに基づいたもの。去年、カール・ユングの本を読んでいて、私はその概念にとても興味をそそられた。というのも、私自身、自分の中に別の存在、女性的な面というのを確かに感じているから。自分が男性であれば男性的部分が優位を占めなければならないけれど、女性的部分も強くあるべきだ。一方、女性であれば女性的部分が支配的であるべきだけれど、男性的部分も強くあるべきで、そこが大事なところなんだ。“counterpart”という意味からすればその両方が良いもので、どちらか一つが良ければどちらかが悪いという価値観のものではないんだよ。 Stick It Outライヴ演奏:Couterparts tour, Test For Echo tour (2nd leg) Neil Peart:“stick it out”という言い回しには二重の意味があって、一つは困難や苦難を耐え抜いてやり遂げるということ。その他に、「表に出す」という意味もあって、「舌を突き出す」という時に使う。何かにしがみついていく強さと同時に、感情を爆発させるような姿勢という逆の意味も持つんだ。この曲ではその両方のことを取り上げ、自分の本能というものについても語っている。自制心にとらわれずに解き放つんだと説く歌が世には沢山出ていて、それはそれで結構だ。だが、あまり真実とは言えない。何故なら本能にまかせていたら、時として間違いを犯してしまうからだよ。例えば多くの人が他人を傷つけようとする怒りや激情の本能にかられる。それは野放しにしていい本能ではない。だから、この曲の中で私は、本能というものは用心深く抑制されていれば良いものであるということを主張しようとし、電光石火のような瞬間の反応についても同じことをいおうとした。反射神経がいいのはもちろんいいことだが、例えば誰かにふいに肩を叩かれて、とっさに振り返って相手を殴ったりしたら(笑)、それはいい反応にはならない。反応が素早いのはいいことだし、確かにドラマーには必要なことだけれど、私がドラムやシンバルに使うのと同じ反応を、人の頭には使うべきではない‥‥(笑)(Burrn! 1994年1月号) Alex Lifeson:あの曲では6弦を D にチューン・ダウンしてあるんだ。そうすると少しヘヴィな感じになる。とにかくヘヴィな曲を書きたかったんだ。オープニングではギターを4〜5本使っていると思うよ。あのフィードバックの部分でトラック・アップしたんだ。本体のギターは3本だと思う。エフェクトとして、いくつかの音を叩いているだけのギターも少し使っているよ。(Player 1994年4月号) Cut To The Chaseライヴ演奏:なし Neil Peart:これは“野心”について。曲の中で私が“It”を使ったところは、総て“野心”に置き換えられるゲディ(リー)がこのようにミステリアスにした方が、歌う分にも聴く分にももっと面白くなるだろうと提案したから“It”としたんだ。やっぱりここでも野心の持つ二つの面を探究している。 Nobody's Heroライヴ演奏:Couterparts tour, Test For Echo tour Neil Peart:私は、ヒーローを崇める人達にとって順当な考え方でのヒーローはどうあるものなのか、そしてまたヒーローという肩書きと暮らす人達にとって順当な考え方ではどうかという事を考えていた。私が最終的に心を固めたのは、ヒーローという概念は、ヒーローを崇める人達にとっても、崇められる人達にとっても、あまり健全ではないということ。ヒーローとは本当は何者かと言えば、超人でもなく、超人的な生活をおくる人間でもなかったんだよ。私にとってヒーローというのは、立派な行為そのもの。たとえば歌詞に出てくる“溺れる子どもを救い出す”とかすれば、そういうのがヒーローなんだと思う。だけど、それはその人が超人だという事じゃない。 Between Sun And Moonライヴ演奏:なし Neil Peart:私と“Tom Sawyer”や“Force Ten”を一緒に作り、以前は MAX WEBSTER というバンドに詩を書いていた、パイ・デュボワという人物と共作した。彼はとても突飛な作詞スタイルの持ち主なんだ。(笑)彼の書く詩はとてもイメージを湧かせるもので、私にも正確にはなにを言わんとしているのかわからないことが多い。それでも彼の描くものの調子というか、言葉の縫い合わせ方が、私はとても気に入っている。この曲についても、私が共感出来るテーマに沿って仕上がった。簡単に定義するなら、“自然”だね。ここに出てくる太陽と月の間にある湖のような自然の安らぎをいかに私達が必要としているか。この湖のような自然黙想に耽るちょっとした時間を象徴している。それは大切なことだよ。私達もツアーから離れて、都会を離れて森の中に逃げ込めば、新たに根を下ろしたような感じを覚える。木々や岩や水に接することが出来れば、それだけできっと私達を穏やかわに返してくれる。 Alien Shoreライヴ演奏: なし Neil Peart:これも“counterpart”の二重性を言おうとしている。男性と女性、お互いにとっての異文化、異人種について。世界中、アジアからヨーロッパ、アフリカ中の至るところを旅してきて、各地にいい友人が出来たり、いい経験をしたりした。そうすると私はあらゆる人が同じような気持ちになるものだと考えがちになってしまうが、誰もがそうだとは限らない。私が感じるのとは違う感じを抱く人がおおいものだという事を悟らなければならなかった。私は、女性を理解しようとする時にしろ、(笑)アフリカの人々を理解しようとしている時にしろ何にしろ、異国の浜辺に辿り着こうとしている気がしてしまう。相手とは自分の人生の一部として関わりたいと思い、自分の体験にもしたいと思って、いつも手を伸ばしている。この曲が語っているのはそういうことなんだ。(Burrn! 1994年1月号) Speed Of Loveライヴ演奏: なし -----"love" という言葉は一般的な言葉で、一見 RUSH ナンバーのタイトルらしくなくも思えたりします。この曲の意図するところは? Neil Peart:(笑)そう、私は“love”にまつわる曲は書くけれど、それは“ラヴ・ソング”の曲じゃないからね。そこが違うんだと思う。それは大切な主題だと思うけれど、大抵はヴァレンタイン・デーのカードのようにもっと感傷的に使われる。特に内容はなくて、これを使えば即、聴く者の感傷を誘えるというものだ。基本的に私としては、人と人とが感情面での関係を確立しようとするにあたってこの主題がどう作用するものかというよりは、それ自体について書く方がいいね。私が言おうとしたのはそれを確立したら、自分でもそれに見合うだけのことをしなければならないし、それは意志の努力によって持続していかなければいけないという脆い状態ということさ。 Double Agentライヴ演奏:Counterparts tour Neil Peart:眠っている時にはいかに心の動きが無意識になるかというアイディアに取り組んでいる。夢はただの幻想のように思えたり、実際に幻想に過ぎなかったりする。だけどその一方で真剣に思考が進行していることもあって、時々私は朝目が覚めると、眠っている間に何かの決断をしていたりするんだ。そんなのはごく特別だし、驚くべきことだけどね。それで、私はスパイの諜報活動のイメージと、とても視覚的なものだということで悪夢のイメージを素材にした。だけど本当は、眠りに入る間際が半ば意識がある状態と半ば無意識の状態のどちらともつながっている唯一の時だということを判ってもらいたかったんだ。それはまた、とてもクリエイティヴな時間だと思う。私もそういう眠る寸前にいいアイディアが出てきたり、はっきりと物事が考えられたりするんだよ。(Burrn! 1994年1月号) Leave That Thing Aloneライヴ演奏:Counterparts tour, Test For Echo tour Neil Peart:レコーディング中、長い間、私達3人で隠遁していると、愉しみからは隔離されてしまうから、みんなで違う形の髭を生やし伸ばし始めたんだ。顎髭を生やしていると、いつもそれをいじってしまうもので、3人で話をしてるうちに一人が髭をいじると、他の誰かが“Leave that thing alone!(放っておけよ!)”と言っていたんだ。(笑)でもあれは一時的なもので、もうみんな剃ってしまったよ。(Burrn! 1994年1月号) Cold Fireライヴ演奏:Counterparts tour Neil Peart:“Speed Of Love”では“愛の速度ほど変化の速いものはないのだから気を付けなければいけない”と言い、“Cold Fire”では“何がそれを変えてしまうのか”の例を挙げている。“Cold Fire”は一組の男女の会話で、男は愛の感傷的で俗受けする面に対する現実の面をよく判っていない。女はこの鈍い男にそこのところを説明しているんだ。(笑)彼女は「私の愛はとどまるところを知らないけれど、あなたがあんまり私をガッカリさせたり、ひどい扱いをしたりしたら、いなくなる」と説明している。言っておくけど、この会話は全部架空で、人物も私が生み出したもので、私自身に起こったことではなよ。(笑)男の方は、例えば彼女がなぜラヴ・ソングが好きなのかも判らなくて、女はそれに対して「ラヴ・ソングはただのラヴ・ソング。だけどこれはラヴ・ソングでもファンタジーでもなくて、私達の関係なの。あなたが自分でも言うように、私があなたらしいと思うように振る舞う限りは、私の愛は強くなる」と説明する。もし相手の目から見て、自分らしくない振る舞いをし始めているように見えたら、もう愛されなくなるものなんだよ。(Burrn! 1994年1月号) Everyday Gloryライヴ演奏: なし Neil Peart:この曲の最後の節は純粋な楽観論になっている。“どんなにこの世の中がすさんでいても、それでも君にはやり遂げられる。どんなに事態が暗くても、それでも君は光になれる”と。これがいつも私の言っていることなんだ。いつも希望がある、自分の夢を追い求めろということを言っていて、そのテーマに私は繰り返し舞い戻ってくる。私は、自分では悲観的になったことはないと思う。ただ現実的にはなる。世の中のそのままの姿を受けとめることはするからね。「それでもみんなそれを超越出来るのだ」と言い、どの曲にも“確かに事態はひどい。でも君はそれを上回ることが出来る”という内容が備わっているんだよ。(Burrn! 1994年1月号) #Nobody's Hero の項も参照のこと |
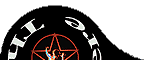 |
The Albums Of Rush index | Home | BBS | What's New? | Links |
|
 |
||